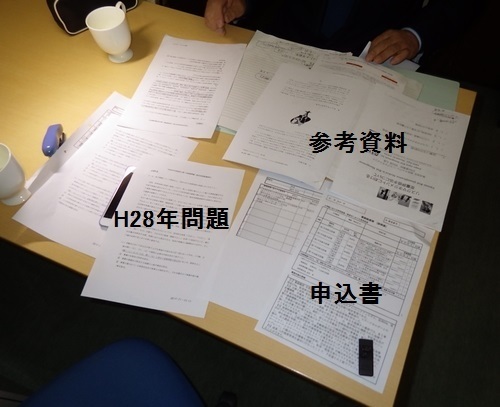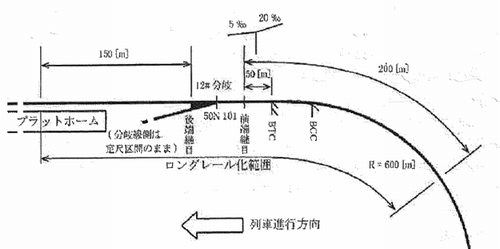問題
鉄道コンクリート構造物は一般に、完成後長期にわたり供用されるため、適切な維持管理により性能低下を抑制することが重要である。鉄道構造物等維持管理標準(コンクリート構造物)で示される検査区分のうち、初回検査と全般検査について、①それぞれの検査の目的、②それぞれの検査の着眼点、③安全を脅かす変状例の3点について注意すべき点を整理して述べなさい。
模範解答(簡易答案)
(1)検査の目的
(1−1)初回検査
初回検査の目的は、新設構造物及び改築・取替を行った構造物の初期状態を把握することである。施工時の欠陥や初期の不良箇所を検出し、本来の性能が確保されているかを確認しなければならない。
(1−2)全般検査
全般検査は構造物全般の健全度を把握するためのものである。目的は変状のある構造物を抽出することや、前回検査で変状が確認された部分の進捗状態を把握することである。経時的な変状が確認されれば、健全度の判定の精度を高めるために、特別全般検査を実施し、早急に補修を行う。
(2)検査の着眼点
(2−1)初回検査の着眼点
初回検査の着眼点は、施工に由来して変形、ひび割れ、剥離、剥落、漏水等の有無および程度を目視により調査する。必要に応じて下記の方法で検査を実施する。
・コンクリートの剥離及び空洞等は点検用ハンマーを用いて打音検査を行う。
・鋼材のかぶりは電磁誘導法等の非破壊検査で確認する。
(2−2)全般検査の着眼点
全般検査の着眼点は、新規の変状を目視で調査するだけでなく、前回検査結果台帳を用いて、ひび割れの分布、支承のずれ、擁壁の傾き、漏水の程度等進捗していないかを確認する。ただし、検査精度を高めるために下記の方法で検査を実施することもある。
・クラックスケールを用いてひび割れ幅を測定する。
・メジャーを用いてひび割れ長さを測定する。
・デジタルカメラで撮影したものをひび割れ解析ソフトを用いて処理することにより、ひび割れ分布図を作成する。
(3)安全を脅かす変状例
①高架橋でひび割れが発展した変状例
・高架スラブで数ミリ以上のひび割れが発生した場合、列車運行により高架橋が崩壊する恐れがある。
・高欄下部のコンクリートに剥離や剥落が生じ、高架下の公衆等の安全を脅かす変状。
②橋梁部で見られる変状例
・桁の斜めひび割れが、支点方向に軸方向鉄筋に沿っているもので、幅が0.5mmを超える変状はコンクリート桁が脱落する恐れがある。
・桁下面において、前面に鉄筋が露出している場合、列車運行により桁が破壊する恐れがある。
完成答案
(1)検査の目的
(1−1)初回検査
初回検査の目的は、新設構造物及び改築・取替を行った構造物の初期状態を把握することである。施工時の欠陥や初期の不良箇所を検出し、本来の性能が確保されているかを確認する。
(1−2)全般検査
全般検査は構造物全般の健全度を把握するためのものである。目的は変状のある構造物を抽出することや、前回検査で変状が確認された部分の進捗状態を把握することである。経時的な変状が確認されれば、健全度の判定の精度を高めるために、特別全般検査を実施し、早急に補修をする。
(2)検査の着眼点
(2−1)初回検査の着眼点
初回検査の着眼点は、施工に由来した変形、ひび割れ、剥離、剥落、漏水等の有無および程度を目視により調査することである。また、ひび割れが発生している場合、クラックスケールによりひび割れ幅を測定し、下記のとおり措置を施す。
①0.2mm以下ならば、必要に応じて監視等の措置を施す。
②0.2mm以上が多ければ、必要な時期に措置を施す。
③数ミリ以上であれば緊急に措置を施す。
(2−2)全般検査の着眼点
①全般検査の方法
全般検査の着眼点は、新規の変状を目視で調査するだけでなく、前回調査との比較により、ひび割れの増加、支承のずれ、擁壁の傾き、漏水の程度等進捗していないかを確認する。目視と合わせて、クラックスケール、メジャー及びカメラを用いてひび割れ等を調査する。
②劣化を想定した検査の着眼点
a中性化:かぶりが小さい箇所や水セメント比の大きなコンクリートでのひび割れには中性化の疑いがある。概観から中性化を特定することは困難であることから、コア採取やはつりによる中性化深さを確認する。
b凍害:コンクリート表面にスケーリングや微細なひび割れ又はポップアウトなどが見られたら想定できる。
cアルカリ骨材反応:建設後10年程度経過したコンクリート構造物で亀甲状のひび割れがあり、表面が変色している場合に想定できる変状である。
d塩害:鉄筋に沿ってコンクリートにひび割れや、剥離が生じてれば塩害と想定できる。その場、部分的にコンクリートを採取して塩化物含有量を調べる。
上記の変状の措置としては、部分的な打ち変えや表面被覆が考えられる。
(3)安全を脅かす変状例
①高架橋でひび割れが発展した変状例
・高架スラブで数ミリ以上のひび割れが発生した場合、列車通過により高架橋が崩壊する恐れがある。
・高欄下部のコンクリートに剥離や剥落が生じ、高架下の公衆等の安全を脅かす変状である。
・コンクリート表面に亀甲状のひび割れがある場合、コンクリート内部で容積膨張し、強度低下が生じるアルカリ骨材反応である。
②橋梁部で見られる変状例
・桁端部側面部において、支承方向に斜めひび割れが、入っているもので、幅が0.5mmを超える変状がある場合、列車の繰り返し荷重により、支点部の桁が剥離・剥落し、桁が脱落する恐れがある。
・桁下面全面に渡って鉄筋が露出している場合、列車通過により応力が桁に集中し、桁が破壊する恐れがある。